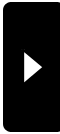2015年09月27日
自然塾7回目(2015年度洞スギ)
ちょっと雨の心配もあった9月27日(日)!自然塾第7回目を魚津片貝川上流の『洞スギ巨木群』にて実施しました。 洞スギで自然塾を開催するのも何度目かになりますが、参加していただく方はその年によって違うので毎回、新鮮な気持ちで塾を開催する事ができます。もちろん、何度も参加していらっしゃる方もいますが、その方々は洞スギの魅力に、おそらく虜になっていらっしゃるのではないかと推察します。

まずは集合場所である山の守キャンプ場にある、ビジターセンターにて洞スギについての説明を行いました。講師は森林インストラクターの近堂さんがメイン講師です。
ビジターセンターから車で奥の駐車場に向かいます。そこから、洞スギまでは約2km強の道のりがあります。アスファルト道路が整備されており、道端の山野草などの解説をしながら、ゆっくりと歩きました。



片貝川上流域にはとてもきれいな清流が流れており、道端にも多くの山野草が群生しています。特徴的な植物を手折ってその植物の名前や人々の関わりいついて、またはその植物の葉や茎、根茎についても近堂さんが解説して歩きます。

洞スギへの散策途中に河原に下りると写真の様な大きな石が川の中に鎮座しています。『龍石』と呼ばれて散策に訪れる人々の目に触れることができます。龍石があるこの地では、とてもきれいな清流が水量も多く流れています。他の河川ではなかなか体験できない、川の水をそのまま飲む事ができる貴重な水がそこに流れているので、その場で喉を潤したり、ペットボトルに入れて散策中の水分補給に使ったりする事ができます。早速、口に含んでみると水道水とは違う、ミネラルがたっぷり含まれているだろう美味しい天然水を味わう事ができます。


龍石の案内板と龍石神社がその地に祀られています。今年はトチの実が大豊作のようで、神社前の広場にはたくさん実が落ちています。その実を踏まないように気を付けながら神社にお参りして、散策を続けました。



洞スギ巨木群エリアに到着! 案内板と散策マップを参考にしてある程度の知識を頭に入れてから、近堂さんの解説を聞きます。洞スギの名前は岩の上に大きく生長して岩を抱え込んでいたスギが長い年月を重ねていくと、抱え込まれていた岩が風化して割れ落ちてしまい、根の部分が洞穴が開いたようになります。その様子から付いた名前が『洞スギ』です。スギは樹木の中でも極めて長命であり、岩が風化しても生き続けるのですね!このような樹木は他にはなかなか無いようですね。

写真の様に岩を抱え込んで成長しますが、私たちが普段見ているスギとは樹形が相当違います。森林に植えられているスギは洞スギから見るとまだまだ、青二才と言える存在なんでしょうね・・・


写真のスギには真ん中に空洞が見えますが、岩が風化してこうなったものと思います。人類をはじめとした、動物たちとは一生のスケールが圧倒的に違う樹木たちなのでその一生でどのような自然を見てきたのかとても興味深いところですね。
そのような事も含めて解説を進める近堂さんは、水を得た魚の様に生き生きとエネルギッシュに次々と話題提供と洞スギに対する熱い思いも語っていきます。

今年は長い間スイス滞在で自然塾も久しぶりだった石崎さんも元気に参加していらっしゃいます。WHOへ娘さんが勤務中ということで、そのスケールの大きな話と、悠久の時を生きてきた洞スギは相通ずるところがありそうですね!

最後に洞スギの前で集合写真を撮りました。カメラマンは石崎さん!
あまり好天とは言い難い一日でしたがご参加いただいた皆様にはお疲れ様でした。心の充実度はMAXになった事と思います。自然塾もあと3回ですが、これからもよろしくお願いします。

まずは集合場所である山の守キャンプ場にある、ビジターセンターにて洞スギについての説明を行いました。講師は森林インストラクターの近堂さんがメイン講師です。
ビジターセンターから車で奥の駐車場に向かいます。そこから、洞スギまでは約2km強の道のりがあります。アスファルト道路が整備されており、道端の山野草などの解説をしながら、ゆっくりと歩きました。



片貝川上流域にはとてもきれいな清流が流れており、道端にも多くの山野草が群生しています。特徴的な植物を手折ってその植物の名前や人々の関わりいついて、またはその植物の葉や茎、根茎についても近堂さんが解説して歩きます。

洞スギへの散策途中に河原に下りると写真の様な大きな石が川の中に鎮座しています。『龍石』と呼ばれて散策に訪れる人々の目に触れることができます。龍石があるこの地では、とてもきれいな清流が水量も多く流れています。他の河川ではなかなか体験できない、川の水をそのまま飲む事ができる貴重な水がそこに流れているので、その場で喉を潤したり、ペットボトルに入れて散策中の水分補給に使ったりする事ができます。早速、口に含んでみると水道水とは違う、ミネラルがたっぷり含まれているだろう美味しい天然水を味わう事ができます。


龍石の案内板と龍石神社がその地に祀られています。今年はトチの実が大豊作のようで、神社前の広場にはたくさん実が落ちています。その実を踏まないように気を付けながら神社にお参りして、散策を続けました。



洞スギ巨木群エリアに到着! 案内板と散策マップを参考にしてある程度の知識を頭に入れてから、近堂さんの解説を聞きます。洞スギの名前は岩の上に大きく生長して岩を抱え込んでいたスギが長い年月を重ねていくと、抱え込まれていた岩が風化して割れ落ちてしまい、根の部分が洞穴が開いたようになります。その様子から付いた名前が『洞スギ』です。スギは樹木の中でも極めて長命であり、岩が風化しても生き続けるのですね!このような樹木は他にはなかなか無いようですね。

写真の様に岩を抱え込んで成長しますが、私たちが普段見ているスギとは樹形が相当違います。森林に植えられているスギは洞スギから見るとまだまだ、青二才と言える存在なんでしょうね・・・


写真のスギには真ん中に空洞が見えますが、岩が風化してこうなったものと思います。人類をはじめとした、動物たちとは一生のスケールが圧倒的に違う樹木たちなのでその一生でどのような自然を見てきたのかとても興味深いところですね。
そのような事も含めて解説を進める近堂さんは、水を得た魚の様に生き生きとエネルギッシュに次々と話題提供と洞スギに対する熱い思いも語っていきます。

今年は長い間スイス滞在で自然塾も久しぶりだった石崎さんも元気に参加していらっしゃいます。WHOへ娘さんが勤務中ということで、そのスケールの大きな話と、悠久の時を生きてきた洞スギは相通ずるところがありそうですね!

最後に洞スギの前で集合写真を撮りました。カメラマンは石崎さん!
あまり好天とは言い難い一日でしたがご参加いただいた皆様にはお疲れ様でした。心の充実度はMAXになった事と思います。自然塾もあと3回ですが、これからもよろしくお願いします。
Posted by tsuru at 20:00│Comments(0)