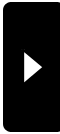2010年11月07日
養成講座第9回(増山城跡)
絶好の講座日和となった今日、「養成講座第9回」を増山城跡似て実施  “古人(イニシエビト)の自然の活用や自然を利用した生き様”を教えてもらうという、これまでの講座とはちょっと趣向の違う講座を開催しました。
“古人(イニシエビト)の自然の活用や自然を利用した生き様”を教えてもらうという、これまでの講座とはちょっと趣向の違う講座を開催しました。

今日の講師の先生方は今年「増山城跡解説ボランティア養成講座」を受講された方々で設立された『曲輪の会』の2名の方にお願いして実施 写真の右端が川辺さんで、左端が津田さんです。曲輪の会自体は先週の戦国祭りのちょっと前に設立された会だけど今日のお二人はそれ以前から増山城跡の事を勉強なさっているので、熱い思いが伝わるとてもいい解説でした。バックにある門は『冠木(カブキ)門』という門です。この門も先月の27日に完成したばかりの門で、近づくと木の香りがします。
写真の右端が川辺さんで、左端が津田さんです。曲輪の会自体は先週の戦国祭りのちょっと前に設立された会だけど今日のお二人はそれ以前から増山城跡の事を勉強なさっているので、熱い思いが伝わるとてもいい解説でした。バックにある門は『冠木(カブキ)門』という門です。この門も先月の27日に完成したばかりの門で、近づくと木の香りがします。

登る前に城跡の概要について看板を使って説明を受けています。

ちょっと登った所で掘切の説明を聞いています。6月には今日のメンバーとは違うけど、砺波市教育委員会の野原学芸員さんからも説明を聞きました。このブログの過去をたどるとその時の様子がわかります。

切岸(郭などを作るときにできた、人工的な急斜面)の説明を聞いています。敵が攻めてきたときに備えていろいろな工夫が成されていることがよく理解できました。

一の丸からの眺望は今日も最高でした!増山の城下町跡が見えたり、遠くは砺波市街地やもっと遠くの山並みもよく見えます。標高が120~130m程度でも遠くまで見えることが山城を作る際の条件の一つなんでしょうね。一の丸からの眺望はいいのですが、皆さんが立っている前は切り立った急斜面であり、敵からの侵入を防いでいたことがこの地形を見るだけでもよく判ります。自然が作り出した難攻不落の地形と砺波・射水・婦負三郡の要所だったことも、ここに山城ができた重要な理由だったことと思います。

お昼に登った亀山城にはソヨゴが大きく成長していました。亀山城から下りる時にも話しましたが、神事に使う樹木としては、サカキが有名です。しかしサカキは日本海側には自生していません。そこで、日本海側では山に多く自生しているヒサカキを神事に使うことが多くあります。もちろん大きな神社には境内にサカキを植えてあることもありますが、富山県では神事というとヒサカキを使います。飛騨地方ではサカキやヒサカキに代わって、写真のソヨゴを使うことが多いようです。
…ということで本日は有意義な時間を過ごせたことと思います。ご参加いただいた受講生の皆様にはお疲れ様でした。今日は各地で、公民館祭りなどがあり、欠席者が多かったことはちょっと残念でしたが、いよいよ今年の講座もあと1回を残すだけとなりました。11月28日が最期の講座です。
 “古人(イニシエビト)の自然の活用や自然を利用した生き様”を教えてもらうという、これまでの講座とはちょっと趣向の違う講座を開催しました。
“古人(イニシエビト)の自然の活用や自然を利用した生き様”を教えてもらうという、これまでの講座とはちょっと趣向の違う講座を開催しました。
今日の講師の先生方は今年「増山城跡解説ボランティア養成講座」を受講された方々で設立された『曲輪の会』の2名の方にお願いして実施
 写真の右端が川辺さんで、左端が津田さんです。曲輪の会自体は先週の戦国祭りのちょっと前に設立された会だけど今日のお二人はそれ以前から増山城跡の事を勉強なさっているので、熱い思いが伝わるとてもいい解説でした。バックにある門は『冠木(カブキ)門』という門です。この門も先月の27日に完成したばかりの門で、近づくと木の香りがします。
写真の右端が川辺さんで、左端が津田さんです。曲輪の会自体は先週の戦国祭りのちょっと前に設立された会だけど今日のお二人はそれ以前から増山城跡の事を勉強なさっているので、熱い思いが伝わるとてもいい解説でした。バックにある門は『冠木(カブキ)門』という門です。この門も先月の27日に完成したばかりの門で、近づくと木の香りがします。
登る前に城跡の概要について看板を使って説明を受けています。

ちょっと登った所で掘切の説明を聞いています。6月には今日のメンバーとは違うけど、砺波市教育委員会の野原学芸員さんからも説明を聞きました。このブログの過去をたどるとその時の様子がわかります。

切岸(郭などを作るときにできた、人工的な急斜面)の説明を聞いています。敵が攻めてきたときに備えていろいろな工夫が成されていることがよく理解できました。

一の丸からの眺望は今日も最高でした!増山の城下町跡が見えたり、遠くは砺波市街地やもっと遠くの山並みもよく見えます。標高が120~130m程度でも遠くまで見えることが山城を作る際の条件の一つなんでしょうね。一の丸からの眺望はいいのですが、皆さんが立っている前は切り立った急斜面であり、敵からの侵入を防いでいたことがこの地形を見るだけでもよく判ります。自然が作り出した難攻不落の地形と砺波・射水・婦負三郡の要所だったことも、ここに山城ができた重要な理由だったことと思います。

お昼に登った亀山城にはソヨゴが大きく成長していました。亀山城から下りる時にも話しましたが、神事に使う樹木としては、サカキが有名です。しかしサカキは日本海側には自生していません。そこで、日本海側では山に多く自生しているヒサカキを神事に使うことが多くあります。もちろん大きな神社には境内にサカキを植えてあることもありますが、富山県では神事というとヒサカキを使います。飛騨地方ではサカキやヒサカキに代わって、写真のソヨゴを使うことが多いようです。
…ということで本日は有意義な時間を過ごせたことと思います。ご参加いただいた受講生の皆様にはお疲れ様でした。今日は各地で、公民館祭りなどがあり、欠席者が多かったことはちょっと残念でしたが、いよいよ今年の講座もあと1回を残すだけとなりました。11月28日が最期の講座です。
Posted by tsuru at 20:50│Comments(0)